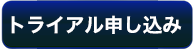社会保険労務士法人 協心 様
全国1300社を超える顧問先に向けて、労働・社会保険の諸問題の解決をサポートしている社会保険労務士法人 協心(きょうしん)では、神戸オフィスの移転、およびフリーアドレス化に合わせて「らくーざ」を導入。その導入の得られた効果について詳しく伺った。

社会保険労務士法人 協心について
協心は、1976年に兵庫県で創業、2016年には法人化され、現在では東京、大阪、福井、神戸、福岡と全国5拠点にて、1300社を超える顧問先に向けて事業を展開している社会保険労務士法人。
「協心・顧客・家族・社会」すべての関わる人へ笑顔を届ける「四方笑顔」を理念に、業種や規模にとらわれない様々な企業の伴走者として、労働・社会保険にまつわる諸問題の解決を「手続き代行」や「コンサルティング」を通してサポートしている。
――らくーざの利用状況を教えてください。
らくーざは弊社の神戸オフィスで、社員の座席抽選に利用しています。
2022年8月に尼崎から現在の神戸にオフィスが移転するタイミングで導入したので、約2年ちょっと使っている形になりますね。
神戸オフィスには現在11名の社員が在籍しており、その中で私と所長を除いた9名が、毎日フリーアドレスのオフィス内のどこに座るかを、らくーざを使って決めています。
らくーざには着席状況の確認や、ゾーニング機能、座席種別機能など、いろんな機能が付いていますが、私たちが使っているのはほぼ抽選機能だけ。
一番ミニマムな使い方をしているのではないでしょうか。
――端末の設置状況、運用状況を教えてください。
オフィスの入口脇に、らくーざ専用のノートPCを置いています。
出社したら、まずそのPCの画面に表示された自分の名前をタップして、「今日の座席」を決めてもらうところから仕事が始まります。
基本的には「毎日違う座席になる」、「昨日とは違う人と隣になる」というロジックの下で抽選を行っています
ただし「仕事が集中しているスタッフには大きなモニターが使える座席」、「新人にはメンターと隣合わせになる座席」……という形で、状況に応じて固定席を設定することもあります。
なお、固定席の設定やロジックの変更などの管理も弊社側で行っています。


◾️オフィス入口に設置されているらくーざ用のノートPC端末
――フリーアドレス導入に至った背景を教えてください。

神戸への移転前、尼崎にオフィスがあった頃は、島型の座席レイアウトをしており、社員は常に同じ場所に座っていました。
そのため社員が喋る相手は、席の近い同じ人だけに限られてしまうという課題を抱えていました。
さらにそんな中、コロナ禍によってソーシャルディスタンス確保のため、座席のレイアウトが「学校の教室」のように机が同じ方向を向いた状態へと変更されました。
これによって社員同士のコミュニケーションはより希薄となってしまったのです。
社員同士のコミュニケーションをどうにか活性化させたい。
そんな思いを抱える中で、尼崎から神戸へのオフィス移転が決定しました。
そんな折、弊社の顧問先で既にらくーざを導入されている企業様に仕事で伺った際に、フリーアドレスを上手く導入されていることを知ったのです。
斜めに動線が引かれた個性的なレイアウトで、部門ごとにゾーニングされていて、社員同士の交流も盛ん。
その様子がとても魅力的に感じたので、改めてお時間を取ってもらって詳しくお話を伺い、フリーアドレスにすることの利点や、らくーざという座席抽選システムがあることを教えてもらったのです。
――フリーアドレスにする利点とは、どういったものなのでしょうか。
ひとつは、そもそもの課題だった「コミュニケーションの希薄化を解消できる」こと。
そしてもうひとつが「オフィス選定の幅が広がる」というものでした。
例えば今後、最大15名のスタッフが神戸オフィスに在籍することを想定した時に、席が固定されているとリモートワークの社員がいても、15席は必ず確保しなければなりません。
しかし、もし常に1~2名の社員がリモートワークするなら、座席は最大14席分あれば問題なくなりますし、同じスペースを使って自由なレイアウトも実現できる。
つまりフリーアドレスを前提にすれば、オフィスの広さや家賃の自由度が大きく広がるのです。 そういう利点を考えると、移転先のオフィスではフリーアドレスにするしかないという方向で考えは固まっていきました。
――フリーアドレスオフィスの座席抽選システムに、らくーざを選ばれた理由を教えてください。
やりたいことをすべて実現できたことが、大きな理由です。
- ・座席抽選ができる
- ・抽選の結果を毎日違う席に設定できる
- ・隣り合う人を毎日変えられる機能がある
- ・状況に応じて席を固定させることもできる
- ・月額費用が安価だった
<選定のポイント>
この取材を受けるにあたって、改めてフリーソフトなどを調べてみましたが、こうした機能がすべて揃っている座席抽選システムは他にありません。
先輩ユーザーである顧問先の企業様にも聞いてみましたが、同じく「他にはなかった」と仰っていたので、弊社としてはらくーざ一択でしたね。
――では競合などはなく、スムーズにらくーざを選択されたのですね。
はい。強いて競合を挙げるなら、手作りの「紙のくじ」でしょうか(笑)。
というのも、実際にオフィス移転かららくーざ導入までは数週間のタイムラグがあって、その時は「紙のくじ」で抽選を行っていたのです。
そのため社内では、「紙のくじ」のままでも良いのはないかという意見も挙がったのですが、毎回紙を折り直したり、固定席を設定する手間を考えると、らくーざを導入した方がストレスなくフリーアドレスオフィスが運用できると考えました。
――らくーざの導入効果について教えてください。

■協心 神戸オフィスの座席状況
らくーざ導入によって得られた効果は、大きく次に挙げる2点です。
●社内のコミュニケーションが活発になった。
まずは、期待していた「社内のコミュニケーションの活性化」はある程度、実現出来たのではないでしょうか。 弊社のオフィスの座席抽選は、場所が毎日変わる上、隣りの人が昨日とは違う人になるという条件付けをしています。そのため、仮にあまり相性がそれほど良くない社員同士でも、喋らざるを得ません。
導入時は、若干の衝突などありましたが、私としては「それで良い」と思って見守っていました。
その甲斐あって、「この人にはこう対応しよう」という学びがあったり、「この人はこんなことを大事に仕事をしているんだ」という発見などがそれぞれあったようですね。
今では、みんなが分け隔てなく交流できるようになってきました。
また個人個人で程度の差はありますが、仕事の円滑な連携にも繋がってきたという手応えも感じています。
●ペーパーレス化が大きく進んだ。
こちらはらくーざ導入、およびフリーアドレス化による副産物的な効果ですが、オフィス移転前から少しずつ前に進めていた「ペーパーレス化」が大きく進みました。
フリーアドレス、かつ毎日違う席に座らなければならないとなると、社員は机に書類などを置きっぱなしにできません。
毎日、出社したら専用の書類用ロッカーから取り出して、退社時には片付けるという作業が必要になります。
「置いておく場所がない」という環境があることで、自然と社員の頭もペーパーレスが前提になったようですね
一気に紙で出力するという作業がなくなっていきました。


◾️オフィス内には私物を入れる個人用ロッカーと、仕事の書類を保管しておく書類用ロッカーを設置
――約2年間、実際にらくーざを使ってみて感じたツールとしての魅力を教えてください。
一番の魅力は、シンプルで分かりやすいところです。
管理画面を触らない一般ユーザーからすると、やることは画面をタップして、抽選された座席を確認するだけ。画面上にビジュアルで分かりやすく示されるので、迷うことがありません。
管理画面を触る立場からすると、メンテナンスの自由度が高い点も良いですね。
ランダムで座席抽選するだけでなく、忙しい人や新人に向けて固定席を用意したり、人が増えたりレイアウトが変わった時の座席表の設定も自分たちでできます。
最近アップデートでインターフェイスが変わったので、その操作に慣れるのには少し時間が必要でしたが、操作そのものに困ったこともありません。
ですので、実はサポートに電話したこともないんです。
――らくーざ導入を検討している方に向けて、先輩ユーザーとしてアドバイスをお願いします。
オフィスに社員が10名くらいいるのなら、フリーアドレスにして損はないと思っています。
弊社のように腹をくくってやれば、ペーパーレス化もきっと進められると思います。
そしてフリーアドレスにするなら、座席抽選システムは、分かりやすいインターフェイスで簡単に使えて、比較的安価ならくーざ一択じゃないでしょうか。
――らくーざは最低利用IDが50アカウントですので、9名で活用している協心様ではIDが余った状態になります。それでも安価だと感じられるポイントはどこですか?
特にオプションなどを申し込まなければ、50アカウントでも月額4500円しか掛かりません。
機能面などを考えると、10名前後しか使っていなくても、十分安いと言えるのではないでしょうか。
――今後の展望を教えてください。
らくーざは、今や神戸オフィスにはなくてはならない存在になりました。
他拠点オフィスでも今後、フリーアドレスオフィスを導入することを検討しているらしいと耳にしたので、折に触れてオススメしようと思っています。
――NJCネットコミュニケーションズに期待することを教えてください。
先ほど、私たちからサポートに電話したことがないとお話しましたが、逆にNJCネットコミュニケーションズさんからは、時々様子伺いのご連絡をいただいています。
売りっぱなしで終わるのではなく、気に掛けてくれている、守っていただけていると感じられる点は、とてもありがたいですし安心できます。
今後も、ぜひこのスタンスは変わらないまま、お付き合いを続けていただけることを期待しています。
企業概要
- 社名: 社会保険労務士法人 協心
- 本社所在地: 東京都新宿区新宿1-26-6 新宿加藤ビル7F(東京オフィス)
- 代表: 吉村徳男
- 設立: 2016年7月15日
- 資本金: なし
- 従業員数: 68名(2024年10月1日現在)
- 事業概要: 労働保険・社会保険事務手続き、給与計算アウトソーシング、助成金申請、就業規則作成・改訂、人事賃金制度構築、人事労務相談顧問、セミナー講師代行
- サイトURL: https://kyoshin.group/
*取材日時 2024年10月